著者情報
編集者 佐々木 純
在宅医療のパイオニア的存在である医療法人社団悠翔会理事長・診療部長です。
筑波大学卒業後、三井記念病院の内科・消化器内科等を経て、2006年にMRCビルクリニック設立。2008年に医療法人社団有翔会に法人化。
概要
本書籍は、在宅医療カレッジ(在宅医療に関わる多職種のための学びプラットフォーム)における21講座(21人の専門者による講義)が抜粋され掲載されています。
厳密には著者は21人の専門者+編集者の佐々木氏にあたりますが、便宜上統一して「著者」として記していきます。
在宅医療カレッジでは「スムーズな多職種協働を通じて、理想の在宅医療を実現すること」を目的としています。一方で専門職は自身専門性の中に閉じこもってしまう傾向があるため、専門外の課題や役割を理解することが重要です。そこで在宅医療カレッジでは専門の枠を超え「気づき」を得ることでそれぞれの専門職の役割を再定義し、理想的な在宅医療・ケアを実現することを目指しています。
本書では、大きく認知症ケア、高齢者ケア、地域共生社会の3章で構成されています。さらに、ポリファーマシー、アンダーナース、オムソーリ、口腔ケア、緩和ケア、入退院支援などの専門職の視点からそれぞれ10ページ程度で事例やその職種が考えたことについて記されています。
本書を読むことで、他の職種の考え方やケースを学べ、新しいを気づきを得る機会になるでしょう。
新しい気づきを得られるとということは、自信ができる範囲の統一的な医療やケアよりも一つ進んだ医療・ケアを提供できる=サービス品質の向上ができるということになります。
「おわり」を勝手に作っている
本書では様々な「おわり」に触れられています。例えば、認知症、終末期ケア、医療崩壊などです。
しかし、その「おわり」を勝手に作っている人や環境があるということです。
この「おわり」の解釈により、これまで当たり前であったことが当たり前でなくなり、より良い医療・介護のサービスに繋がるというケースがあります。
認知症は他人が「おしまい」にしている
認知症と診断されることで周りの人たちは本人を人扱いせずにおしまいにしてしまいます。
本人が出来ることでも周りの人がやってしまい、本人のできることを奪ってしまいます。
その結果、本人は意思や自信を失ってきます。そして、暴言や不穏と言う周辺症状へ繋がっていきます。
つまり、間違ったケアの結果として周辺症状が出ているという考え方です。
間違ったケアを続けると良い結果は得られませんので介護者はやりがいを感じられなくなります。
本人に自信を付けられるよう、本人のことをしっかりと理解する必要があります。
一緒にやる自立支援
2000年以降の介護保険制度の開始以降も、それまでに行われてきた様々な「お世話」を営利法人がそれぞれ真似をして、検証もアップデートもされないまま「業務」としています。
グループホームを運営する「あおいけあ」では高齢者はお世話する立場ではなくて、一緒にご飯の準備、掃除、洗濯などを行うこととし、一緒に生活する支援をすることで自立支援としています。
あおいけあでは利用者も介護者もいききしており、3年以上離職者がゼロということです。
スウェーデンのオムソーリ できることは奪わない
認知症の人たちが皆で共同生活をしたら症状が改善されたという1980年代の事例を元に、それまでのケアの在り方の反省も踏まえ療養型病床の運営指針が見直されています。
この運営指針にはオムソーリの考え方が入っています。オムソーリとは、「援助する」「面倒を見る」と意味に加えて「同情する」「気づく」「心を同じくする」などの意味があります。
オムソーリのケアは自立の支援で、本人が出来ることは手伝いません。できないことをだけを見極め非マニュアル的に機転を利かせてケアをします。
「快」の領域にアプローチする認知症ケア
本人と介護者、快と不快で作った2×2のケアフレームにおいて、「介護者の不快」ゾーンの相談が山ほど挙がってくるため、どうしても「不快」にスポットが当たりがちです。
しかし、本人も介護者も「快」となるゾーンを増やす考え方を、ペ ホス氏は唱えています。
「快」を増やすためには介護を受ける本人に関心を持つことが重要です。
【当ブログ著者より一言】
日本では効率的に画一的に質の良い製品を大量生産するという考え方が強いと思います。そのため何でもマニュアル通りにしないと心配になる人が多いと思います。介護サービスにもその考え方は根強いものです。
オムソーリにあるように、注目されているのは非マニュアル的なケアですが、これはまさにホスピタリティでしょう。
そして、ホスピタリティを実現するためには組織として一人のスタッフの自律性を尊重する考え化や、心理的安全性が必要になるでしょう。
さらに、介護を受ける方を自分の家族のように考えて興味を持ち、その方が喜ぶことはどんなことだろうかと考えるのです。
ホスピタリティについては下記書評で記しています。
「おわり」の医療
終末期医療ではスピリチュアルな考え方が必要になってきます。
本書中では「他者との関係が自己を作る」ことから「死を迎える患者にとっての大切な他者との関係性を成立できるように支援していくこと」や、「死は終わりではなくつながりがあるものだ」という死生観について、ケアタウン小平クリニック院長の山崎章朗氏は記しています。http://www.yushoukai.jp/clinic/kodaira/
また、医療法人ゆうの森理事長の永井康徳氏は「自分たちが行うサービスが患者さんにとって一番大切なわけでは「ない」」記しています。患者にとって一番大事なのは自分の生きがいや家族、最期の方に医療サービスが来ます。
よって、本人の生きがいや家族のことを考えて対応しないといけないですし、そのためには医師のみでは難しいことも多くなるため多職種チームで患者を支える必要があります。
さらに、「最期の瞬間に医師は居なくて良い」と医師が看ておくことに価値はなくて一番大事なのは本人が楽に逝けることことと思います。これを家族に説明しておくことで家族は安心しますし、不安ならいつでも連絡してくださいねとしてもいます。
夕張市の医療の「おわり」がもたらしたもの
夕張市では若い世代が去り、高齢者が留まることで高齢化率は48%(日本一)となり、2007年に財政破綻しました。夕張市の病床は171から19となり、医師も多くが去り、CTもMRIも市内に一台も無くなりました。医療崩壊が起こったのです。
その8年後、夕張市の心疾患での死亡率は低下、肺炎での死亡率も低下、死亡数は横ばい、増えたのは老衰による死亡でした。脂肪総数のうちの老衰の割合が0.93%(2005年)→14%(2012年)に跳ね上がっています。
これは病院要らずで最期まで元気に暮らせる地域を作るための方法として一石を投じるものとなってます。
夕張市では医療崩壊後は、肺炎球菌ワクチンや口腔ケアを推し進めることで肺炎で死亡しなくなりました。これは自分の身は自分で守るという意識ができた結果と言えるでしょう。
また、地域における「きづな」を大事にし地域と高齢者との信頼関係を構築することで高齢者はいきいきと過ごすようになりました。そして、医療者は病気を治すというよりは生活を見ていくサポーターという存在になっています。これは地域医療の再構築と一例となっています。
まとめと感想
在宅医療は外来や入院医療と比べると歴史が浅いものです。
近年は、医療費の抑制(入院費の抑制)のためにも、在宅医療の診療報酬を手厚くすることで在宅医療の担い手は増えてきていますが、在宅医療のあるべき姿まだまだ日本国としても手探り状態だと思われます。病院での入院医療と、地域で見ていく在宅医療ではリソースや目的に違いがあるためです。
その中でも、在宅医療の好事例が蓄積されてきているのは事実です。病院では病気の治療にスポットが当たりがちですが、在宅医療では個人のlife(人生・生活)も考慮する必要があります。病気の治療と個人のlifeの狭間で、良い落としどころを見つけるのは在宅医療に関わる医療者としての腕の見せ所なのだと思います。
そのためにも、様々な視点から多くの事例を学び、病院のガイドライン中心の統一的視点にならないようにするのが重要です。本書ならびに在宅医療カレッジは、統一的視点の医療にならないようにクリエイティブな思考にするように存在するのだと思いました。
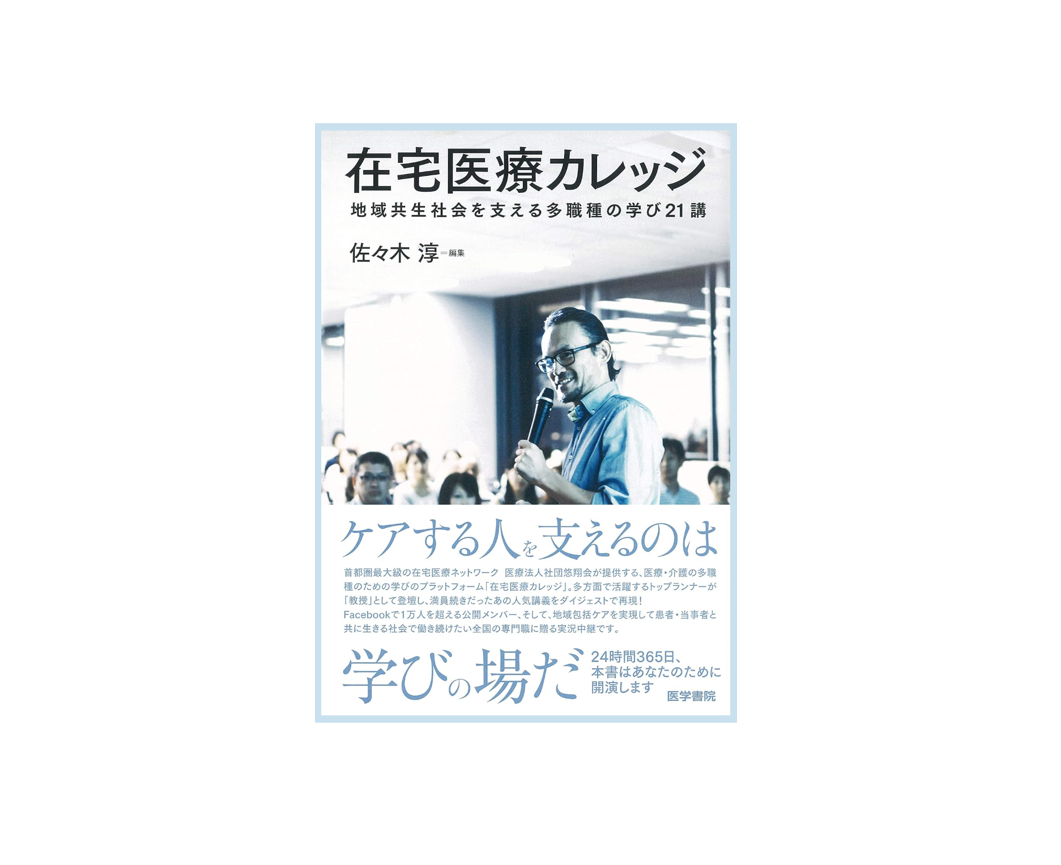




コメント