著者情報
美容医療業界で有名なSBCメディカルグループの代表です。
日本大学卒業後に麻酔科での研修後に美容外科に勤務。その後ご自身で2000年に神奈川県藤沢市に湘南美容外科クリニックを開院しています。
20年で101院を展開するに至っています。
現在は美容から自由診療全般、保険診療、病院までその事業領域を拡大しており、経営支援も行っているようで、WEBサイトには次のように記されています。
「病院経営、専門医療、美容医療、商品開発、保険診療から自由診療までのトータル医療サービス に関するマーケティング、商品企画、人材派遣、他トータル経営コンサルティングを提供しています。」
概要
著者が代表をつとめるSBCメディカルグループホールディングスは2024年の9月にアメリカの株式市場NASDAQに上場をしており、日本国内では最も勢いのある医療グループの一つと言えるでしょう。
「2035年に1000クリニック&100病院を目指す」と本書の著者紹介欄にも書かれており、この目標のために今後も国内外へ大きく価値を提供していくことを目指している姿勢がうかがい知れます。
このように事業を大きく動かしていく
本書タイトルは『究極の「三方良し」経営』ですが、SBCメディカルホールディングスWEBサイト内の代表メッセージにも同じく「究極の三方良し」を実現すると記されており、企業理念にもなっています。代表の相川先生のブレない目標が常に定まっているのだと感じられ、本書にはこの点についてもしっかりと記されています。
他にも、リーダーやマネージャーに必要な考え方やテクニック、売り上げを拡大するための戦略等についての記載があり、クリニックの立ち上げの方から大きな医療グループを作っていくことを考えている方まで参考になる情報が本書には記されています。
自分自身のマネジメント
【当ブログ著者より一言】
自分自身をマネジメントするという部分が、相川佳之という個人、そして巨大グループを作り上げている本質であると感じました。
目標のために自分自身をマネジメントする方法論から、それをスタッフや医院経営へも繋げていっていると感じます。
一番になると目標設定して努力する
本著者は大学時代はテニス部に所属していました。当初は医学部に入るようなやつにはテニスで負けるわけがないと著者は思っていましたが、結果が出ませんでした。
そこで著者は誰よりも練習し4年生の時には優勝しています。
この経験は著者にとっては、自分で一番になると目標設定して苦労そしてナンバー1になった初めての経験ですが、この経験が後のクリニック経営にも大きな影響を与えています。
「自分は努力すれば結果が出る人間なんだ」と気づきを得られています。
やりたいという考えと自分の言葉を一致させる
著者は自分自身を見つめるためにセミナー等にも足を運んでいたようです。
しかし、本当にやりたいことと、それを言葉に出している自分で8割くらいは一致しているものの2割くらいはずれている気がしていました。
そこでアチーブメント株式会社の青木仁志氏が行う「頂点への道」講座に出会うことで、自分の重いと言葉一致し迷いが無くなっていきます。
なぜ迷いがあったかというとやりたいことが明確ではなかったからです。抽象的なビジョンを数字で落とし込めるような具体的なビジョンに変えました。
ゴールを具体的にすることで、10年後、5年後、3年後、1年後、今日の目標が明確になり判断ができるようになるということです。
誠実であること
著者は本書内で「誠実」もしくはそれに近い言葉を多く使用しています。
不誠実な美容医療業界
2000年当時は美容医療業界は顧客にとっても働く人にとってもグレーな業界と見られており、実際、お金を持ってそうな顧客からは高い価格を提示するような不誠実な価格体系が蔓延していました。そこで湘南美容外科では顧客によって変化する不誠実な価格設定をなくしました。
そしてグレーな美容医療業界をオープンにすることで良い人材も入って来られるようにしたいと考えました。これが本書のタイトルでもある「究極の三方良し」に繋がっているということです。
嘘をつかない
著者自身が「私がとても大切にしているのは、誠実さ」と記しています。
とくに経験を積んでいる成功者などには、見栄を貼ったり、言い訳をすることは見抜かれてしまうため等身大のことを正直に話すようにしています。
そして、スタッフに対しても素直なリーダーであるようにしています。
【当ブログ著者より一言】
この「誠実である」ということは人として当然のように感じられるのですが、案外できていないことも多いものです。
約束を守る、謝罪する、感謝するなど子供のことに教えられたことは、大人の顧客や従業員にとっても同じく大事なことだと思います。
当ブログ著者も誠実であることを忘れないように自分自身に言い聞かせ、会社のValue(行動指針)にも掲げています。
開業して学んだリーダーシップとマネジメント
スタッフとの信頼関係づくり
著者ははじめてクリニックを経営してみてスタッフがこんなにいうことを聞かないのかと驚いています。
経営者である著者が給料を払っているのだから当然スタッフは言うことを聞いてくれると思い込んでいました。
表向きは言うことは聞いているのですが、心の底から聞いているわけでは無いということです。
とくに女性スタッフの多いクリニックならではで、ある本で「女性の中でリーダーシップを取るには、好かれたり、尊敬されたりしないとムリ」ということを学び、著者は積極的に食事に行ったりすることで信頼関係づくりを行っていきました。
組織はリーダーで決まる
リーダーの考える基準が高ければ、その周りの人たちはそれに引き上げられ組織全体のレベルが上がっていきます。
そのために、リーダーは実績を作り見せる必要があります。そのためにリーダーは情熱を持って働き、その姿勢を周りに見せていかなければなりません。
これは著者のテニス部時代でも同じで、キャプテンとして誰よりも練習し、個人優勝という実績を見せることで周りが付いてきたということです。
数値化して評価する
新規開院するクリニックの院長はSBCグループでは公募で行っているようです。その際には売上、顧客満足度、スタッフ満足度など数値化されたデータから判断するようにしています。
例えば売上が高い院長ということだけで判断すると、顧客満足度やスタッフ満足度が低い院長の場合長期的には売り上げを下げることが分かっています。
NPS調査や覆面調査など顧客満足度調査を行い数値化しています。
理念採用を徹底
著者グループでは三方良しの理念に共感してくれる人を採用しています。
著者は次のような例を記しています。
1つの船に同じ目的地に向かう人たちが乗っていれば何の問題なく最短ルートで船は目的地に向かうのですが、乗客の目的地がバラバラであった場合は乗客同士のいさかいが発生し、お互いに不快を感じたり船も迷走する。
優秀でも理念の価値観に繋がっていなかったスタッフは辞めていき短期的には苦しい思いもしましたが、目的が同じスタッフが集まることでさらに強い組織になったということです。
この考え方は「人は変えることはできない」ということを著者は理解したためもあります。
そして、人事評価制度も作っています。
人事評価制度はスタッフの未来を確約することです。スタッフは将来が見えることで安心して仕事ができます。
ただ、これができるくらいの余力や資金が無いと確約はできない。それでもスタッフが将来を見通せる人事制度を作るべきと記しています。
売り上げ高は人気投票
顧客が増えることは人気が上がっているということ。人気が上がれば売上高は上がります。
自院への集客はもちろん、顧客を増やすために市場の拡大を考えています。
マーケティング力
著者は開業後は顧客が来ないことに対して様々な行動を起こしています。例えば、自作したチラシを自分や知り合いの協力を得て配布すること、新聞の折り込みチラシや地域密着型のフリーペーパーなどです。
自分でチラシを作り行動することで、リスク覚悟で他とは違く広告にしたり、自分の強みを明確にすることで差別化ができるようになりました。広告のキャッチコピーや写真を変えたりしながら工夫をするうちにマーケティングの力が磨かれていきます。
そしてこれが成功するかどうかの大きな分かれ道でした。
リピーターを増やす
著者クリニックでは脂肪吸引が売り上げに大きく貢献していました。
脂肪吸引は範囲が広く、お腹、次は二の腕というように部位ごとに吸引をします。よって顧客がリピートすることが多くあります。
レーシック手術や歯科矯正などは一度治療を行うと次はありませんので一発型のビジネスです。一発型のビジネスは常に広告費をかけて新規の顧客を獲得する必要があります。リピーターであれば2回目以降の広告費は不要になるため効率がよくなります。
リピーターの多い治療か、1回限りの治療かは経営において大きな差となります。
リピーターを増やすために「3回通った人はブランドスイッチしづらい」という手法も使っています。そのため、いかに3回通ってもらえるかをプランニングし3回セットのメニューも作っています。
顧客にとってのコスパの良さを追求する
リピーターが増えるようにするためにはシンプルに顧客にとってコスパが良いかどうかに尽きます。出したお金にたいして「得したな」と思ってもらえることが重要です。これは500円であっても100万円であっても同じです。
まとめと感想
本書は美容医療の自費診療で大きく飛躍したクリニック経営に関する内容がメインとはなっていますが、保険診療でも大いに参考になる内容でした。
とくに、リーダーシップやマネジメント面では多くの院長先生が苦労されるところですから、大いに参考になると思います。その内容が「三方良し」=「お客様良し」「スタッフ良し」「社会良し」という本書タイトルに現れています。三方良し(「売り手」「買い手」「社会」の3者全員が満足する)は近江商人の経営哲学としてよく引用されますが、相川先生のいう三方良しは「売り手」の部分が「スタッフ」になっているという部分が注目です。もしかしたら究極の三方良しとはスタッフマネジメントにあるという言葉なのかなと思いました。
医療は人による労働集約型の産業ですから人を重視する経営となっていくのかもしれません。
また、本書ではマーケティングの重要性についても述べられています。
マーケティングについては保険診療では軽視されがちですが、自費でも保険でも共通して経営にとっては重要なファクターである考えています。良いサービスを提供していても知ってもらえないと意味がありません。知ってもらうためにどうするかというところからマーケティングが始まります。
(参考)集患マーケティングで参考になった書籍
【書評】『“集患”プロフェッショナル 2016年改訂版~腕の良い医師が開業してもなぜ成功しないのか~』 柴田雄一
たまたま、SBCの保険診療部門出身の先生(現在は独立開業されています)とも出会う機会がありました。その先生から聞いていた「相川先生伝説」のようなものと一致している内容が多く、本で書いているだけではなく普段から本の内容を実践されている先生なんだぁと思います。
改めて自身の目標を叶えるために、いかに具体的に見える化し行動するかが大事なのだと気づかされます。
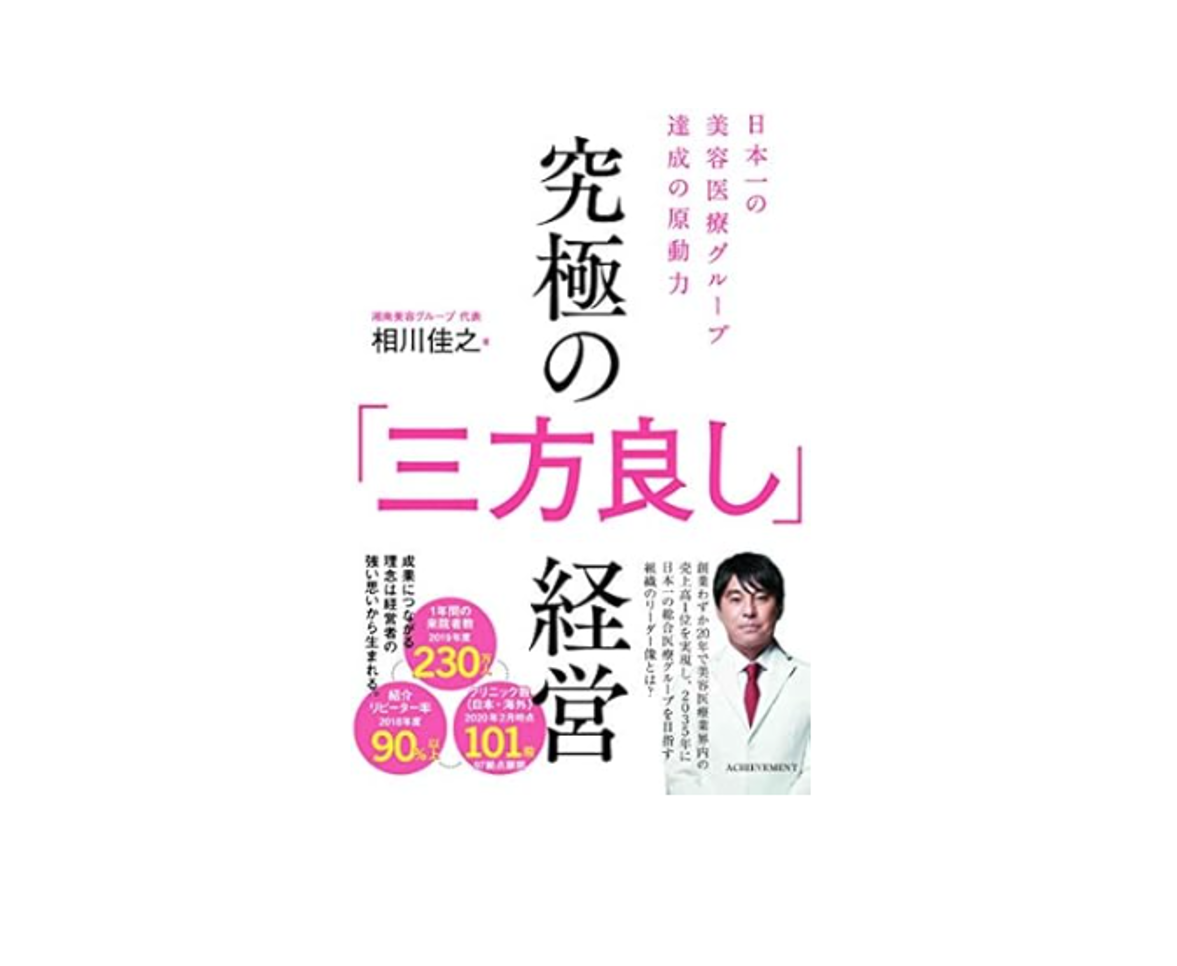




コメント