著者情報
柳 尚信
株式会社レゾリューション、株式会社メディカルタクトの代表取締役です。
株式会社メディカルタクトは主に病医院経営コンサルティングやレセプト請求代行を行っています。
概要
当書籍はタイトルが「クリニック経営はレセプトが9割」のため、レセプト請求における算定漏れ防止や加算などの請求金額を上げるテクニックが書かれていそうに感じるのですが、そうではありません。
すでにクリニック内に存在するレセプトから経営を見える化しマーケティング戦略をたて実行していく事、そして持続可能な経営を行っていくためのマネジメントについて記されています。
加算や請求の漏れは完璧だとしているクリニックでも参考になる部分は大いにあります。もし、このようなクリニックは読んでみても良いでしょう。「100点のレセプトにする必要はない」(第4章)にある費用対効果に関する部分は参考になるかもしれません。
人口減少時代に突入し今後は受診人口が減っていきます。このような時代において生き残っていくクリニックになるためにはどうすれば良いかという広い視点で書かれている書籍になります。
実際のクリニックの事例も記されているためイメージがしやすいと思います。
レセプトデータは自院のことが分かる宝の山
医学と同様にクリニックの経営も科学です。
すなわちデータを利用して現在の状態を見える化し、将来の目標を実現するために打ち手を打って行くものです。
実は、多くの院長は現在のクリニック状態を客観的に理解できていません。
例えば実際に内科クリニックの院長に「糖尿病の患者は1か月に何人くらいいますか?」と聞いても、「結構います」「かなり多い」という曖昧な回答しか得られないことは多くあります。院長は体感として多いとは感じているのですが、実際の数字は答えられないのです。
また、特殊な疾患例がある場合にも同じことが言えます「うちは〇〇の患者が多くてくてね」と言われレセプトをチェックしたところ1か月に2名しかいないということがよくあります。
経営者として経営を科学とするためには経営インパクトの大きい病名の患者数の概数はしっかりと把握しておくべきことになります。
ABC分析で自院の個性を把握する
ABC分析とは売上構造をA・B・Cの3つのグループに分類して管理する基本的なマーケティング手法です。重点分析とも呼ばれます。
ABC分析の目的は売れ筋が高く重要度の高いグループを優先的に管理し売上改善を目指すことにあります。
これは一般的に売れ筋の高いグループの上位2割が、売り上げ全体の8割を占める法則(パレートの法則)による観点から考えられています。
本書では主病名を患者数の多い順に並べ、合計患者数の8割にあたる主病をピックアップすると10件前後の主病名に絞られるだろうと記しています。
この2割の主病名に該当する患者さんは「重要患者」であり、診療の質の向上を考えるべきです。
他にも、「診療行為別集計表」「モダリティ別稼働率」「初診・再診比率」「来院患者属性(年齢・主病、来院時間等)」でABC分析ができ、経営の見える化を行うことが出来ます。
ABC分析については下記書籍でも触れられており、ABC分析について記しています。下記書籍では地域連携先をABC分析にかけて営業戦略を立てています。
自院の個性を磨き上げルーチンとする
クリニックの売上の屋台骨になっているのは上で挙げた2割の患者さんになります。
この2割の患者さんに対して質の高いルーチン診療を提供できるかが重要です。
本書では野球選手を例に出して次のように表現しています。
テレビ等で取り上げられるファインプレーについ目が行きがちですが、(中略)「守備の名手」と呼ばれる選手は皆、そういった”平凡”なプレーこそ大切にしているはずです。基本に忠実に、さほど難しくない打球をミスなくさばくことが、実は一番の”ファインプレー”だからこそ試合で使い続けられる
クリニック経営はレセプトが9割 柳 尚信(幻冬舎)より引用
例えば内科クリニックでは「検査」が収益の6割を占めていると分かります。これを重点項目と認識し、2割の患者さんに対して抜けなく漏れなく検査を行っていく事、そして検査を行う重要性や結果をしっかりと患者さんに伝えていく必要があるのです。本書では生活習慣病患者への具体的な対応方法について具体的に記しています。
結果的に自院の得意分野は磨かれてき、地域の中での立ち位置がはっきりと確立されていく事になります。これはブランディングに他なりません。
クリニックのブランディングについては下記書籍が参考になります。
見える化からはじまるマネジメント
本著者はレセプト代行や教育を行っている会社の代表でもあることから、レセプト請求やスタッフ教育から見たクリニックマネジメントについても記しています。
院長業務を減らす
院長は医師であり経営者であるため、診療時は診療に、診療後に事務作業などと、常にタスクに追われています。
経営者として自院の持続的に運営していくためにの手法として、「任せる」こと「属人化させない」ことを挙げています。
任せる
院長が行っている業務を他の人や会社に移管します。
例えばカルテのチェックや主治医意見書の下書きなどの事務作業は事務員でも可能です。
他には、月初のレセプト請求はレセプト請求代行業者、給与計算は社労士、領収書作業は税理士に委託することも考えられます。
属人化させない
クリニックではついつい1人の「仕事が出来る人」に業務を属人化させる傾向がありますが、これはリスクでもあります。退職や謀反なども起こりえるのです。
そのため、複数人が同じ業務を行えるようにすること、とくにレセプト業務は得意な人に偏りがちなので研修等を行うことで複数人がレセプトをできるようにすることは重要としています。
人材マネジメントの仕組み化
先に記したように外部委託や外部研修を入れることで、万が一誰かが居なくなっても業務がまわるようにしておきましょう。
クリニックの経営において最も多くを占めるのは人件費です。人材マネジメントはクリニックでも大きな影響を与えます。
とくにスタッフ給与に関してですが、経営者としては「稼げるなら給与を出してあげる」とういうスタンスになりがちでスタッフにも利益追求しがちですが、本書ではそれを明確に否定しています。
あくまで、患者満足の向上→利益が増える、という順番を示さなければなりません。そして、評価は個人に帰属させるのではなくクリニック全体に帰属させる方がうまくいくと記されています。
院長とスタッフは視座が異なる
「地域一番のクリニック」などの曖昧で抽象的な言葉は捉え方が人によって変わります。
一番とは患者数なのか?それとも患者満足度なのか?
とくに院長をスタッフでは視座が異なります。別の生き物と考えた方が良いでしょう。
院長はクリニックの経営のために必死で働きますが、スタッフは自分の生活が優先でいかに楽をするかを考える方が多いものです。
このような別の見方をする人が一緒に仕事をしていくためには「言語化」「数値化」が重要です。
抽象的な言葉はできるだけ具体的に言語化・数値化しないと両者の認識はあわないままです。
地域一番のクリニックになるために、「待ち時間を〇%少なくしましょう」といった具合です。
まとめと感想
本書は基本的には経営を見える化することがテーマになっていると感じられました。
見える化されて初めて次の判断が出せるのです。
例えば、現状の売り上げを見える化することで売上拡大戦略を考える。人材マネジメントを勧めるために自院の目標を見える化して共有するということです。
本ブログ著者も昔はそうだったのですが、同じ職場で働いているとついつい「あの人も同じように考えてくれているだろうなぁ」と思ってしまいがちです。
ところがどっこい同じ職場なので似ているとはいえ、考え方のベクトルはその人が生まれて育ってきた環境が異なるがごとく、少しずつ異なります。さらに、経営者とスタッフとでは大きく異なるのは言うまでもありません。
同じ共通認識を持てる状態=具体的で明確な言語・数値を共有することで考え方の異なる者同士の業務はうまく進んでいくのです。
レセプトデータは、経営者にとってもスタッフにとっても共有の具体的に言語化数値化された最も分かりやすい一つのツールと言えるでしょう。



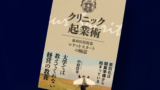


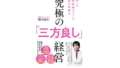
コメント