著者情報
矢野 好臣 / 余語 光
株式会社名南経営、名南M&A株式会社、名南コンサルティングネットワーク アドバイザー。
医療・介護業界に特化したM&Aコンサルティング業務に関わっています。

概要
タイトルには病院(病床数20以上の医療機関)と表記ありますが、診療所(病床数20未満の医療機関)に関しての情報も入っているM&Aに関する書籍です。
最近はM&A(事業の売買など)はかなり一般的な言葉になってきましたが、まだまだ医療業界に居る人にとっては?という方も多いと思います。
経営している医療機関を引き継いでもらいという方(譲渡側)、医療機関を新規に買ったり増やして事業を大きくしたいという方(譲受側)にとってM&Aは一つの選択肢となっています。
本書はアドバイザーの視点から、医療機関(医療法人)のM&Aに関わる譲渡側・譲受側の両者に必要な基礎知識と実例がまとめられています。
M&Aについて基礎的なことを知っておく事は、医療経営を行う医師全てにとって事業の選択肢を増やすことに繋がりますし、実際にM&Aに関わる上での不利益を予防する手法ともなります。
下記書評は実際に新規開業をM&Aで行った先生の書籍レビューです。
【書評】『独立を考えたらまっさきに読む医業の承継開業 ーー第三者承継開業のすすめ』伊勢呂 哲也
また、下記書籍では相続等を考えた承継に関しての内容やM&Aを想定して事業を行うことの重要性について出口戦略を含めて記されています。
【書評】『医療経営の教科書 事業承継・M&A編』 医療経営研究会
医療法人のタイプ
病院の経営主体には自治体や組合、学校法人など様々ありますが、最も多いのは医療法人で約70%を占めます。
また、医療法人にも財団と社団(人を基盤とする)がありますが、99%は社団です。よく目にする「医療法人社団」というのはまさにこれです。
さらに、社団の医療法人は出資持分の有無で分かれますが、2007年4月以降は出資持分無しの医療法人のみしか設立できなくなっています。
なお、現在は医療法人のうち約70%程度が出資持分ありの医療法人とされており、日本は税制優遇措置等を行うことで出資持分なしへの移行を促しています。(経過措置型医療法人)
そして、この出資持分によって、M&Aのスキームに差が出てきます。
基本的には税制優遇の側面から退職金スキームとなる
法人を譲渡する際には多くの場合理事長や理事の退職金として、譲渡金額が支払われます。
これは税制的に有利なことが多いためです。
ただ、出資持分が存在する医療法人の場合は出資持分の買取という概念が発生するため、出資持分も考慮したスキームが必要となります。
出資持分はどう影響するか?
上に記したように医療法人には出資持分の有無というのがあり、何となく「出資していること=その分の価値がある」ように感じてしまうのですが、基本的には譲渡額の合計算出には影響しません。
株式会社では株式の総額と保持している資産と負債等で譲渡額の金額ベースが算出されますが、医療法人では意味合いが異るということです。
譲渡金額の総額は変わらない
譲渡金額は売り手と買い手との交渉により決まります。病院の場合1床当り1000万円という相場はよく聞かれましたが、これはとても乱暴な設定の仕方です。
時価純資産に加えて「のれん」(事業としての価値)等を計算したものになります。
よって、結果的には、まず譲渡金額が決定することになります。そして、もし、出資持分がある場合は譲渡金額は出資持分の金額と退職金の金額に振り分けられます。出資持分が無い場合は退職金のみとなります。
例えば、譲渡金額が1億円と決まり、出資持分の金額が1000万円であった場合はスキームとしては、出資持分金額1000万円、退職金9000万円という形で振り分けられます。
M&Aまでのステップ
本書では定番のM&Aにおけるステップや、アドバイザリー業者の手数料、どのようなスケジュール感で進むのかが記されています。一例として次のようになっています。
- M&Aの相談
- アドバイザリー契約・・・手数料(成功報酬、着手金+成功報酬など)や算出方法(レーマン方式)
- 候補先の探索と資料作成・・・譲渡側資料であるノンネームシートやティザーというものを作成します
- 条件交渉・・・面談や見学、金額概要算出など
- 基本合意・・・譲渡金額やスキーム、スケジュールを定め、M&Aを進めていくというお互いの意向を確認するために基本合意契約を結びます。
- デューデリジェンス(買収監査)・・・財務、法務、労務、ビジネスの観点から細かくチェックします。本書では具体的になされる業務についても記されいます。
- クロージング・・・最終契約、決済
- PMI・・・引き渡し後のスムーズな移行統合作業
良い事例と悪い事例から学べる事
本書ではよくある下記6つのパターンに対してそれぞれ良い事例と悪い事例で合計12の事例が記されています。
- 後継者不在のケース
- 経営不振のケース
- 理事長の事業意欲減退のケース
- 事業の選択と集中のケース
- ファンドへの譲渡ケース
- 出資持分無しのケース
多くの典型的なケースを紹介してくれていますのでとても参考になるのですが、本書で共通して重要だと述べているのは「M&Aの目的を忘れない」ということです。
M&Aではステークホルダーも多くなり、検討事項が増えるのですが、その事項同士がトレードオフの関係になることも多くあります。あちらを立てればこちらが立たず状態が多数複合されるということです。
そのような中最善の意思決定を行うためにはM&Aを行おうと考えたときの目的に立ち返ることが重要です。例えば地域医療の継続というのが目的であれば、譲渡金額面やスタッフ雇用の面で一部は目をつむらなければなりません。
この目的からブレてしまったてまに、買い手との交渉が成立せず、最終的には閉院してしまったというケースもあります。
まとめと感想
医療機関のM&Aで譲渡する側、譲受する側の両側にとっても押さえておくべき基本的なポイントを網羅した書籍はあまりないため、本書を読むことで体系的な知識を得られると感じました。
また、事例も多く掲載されているため、この事例に似た医療機関も存在していると思います。
もし、事例と課題感が似ているようであればその選択肢としてM&Aも考えても良いのでしょう。
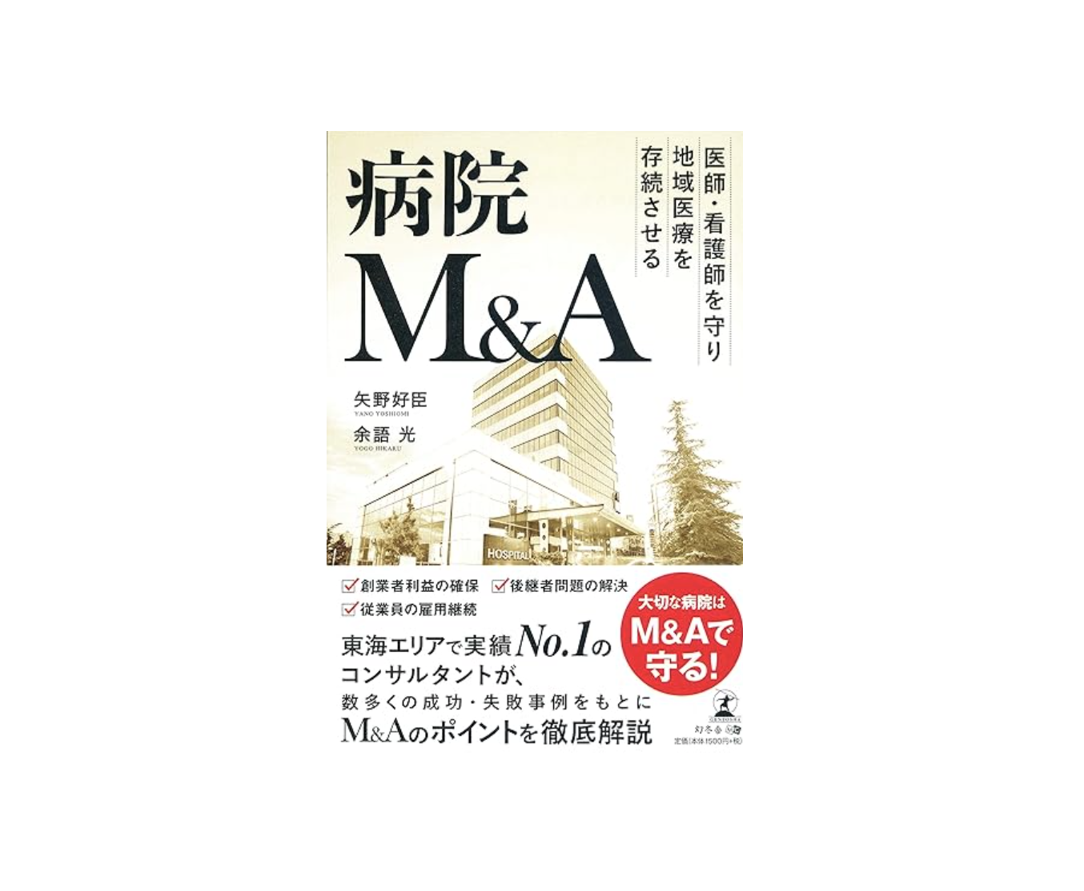



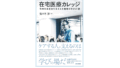
コメント