著者情報
■森 一成
社会福祉法人合掌苑理事長。
元はコンピュータプログラマーで30歳で合掌苑という介護の世界に転身。
創業者の元で弟子として総務等の仕事を行いながら、複数の施設を次々と開設し、18人だった職員は10年程度で6000人の職員を抱えるまでになっています。
■渡邊 佑
合同会社Coaching4U代表。
かつては京セラのコンサルティング会社である京セラコミュニケーションシステム株式会社でアメーバ経営コンサルティングに従事。
コーチングや組織変革コンサルティングを提供しています。
概要
合掌苑自体は昭和28年より第一種社会福祉事業として創業していますが、ルーツはお寺で東京大空襲で身寄りのない方が集まってできたということです。老人福祉法がまだ施行されていない時代から存在する創業者の思いや歴史の深い施設です。
創業者の市原氏は瑞宝章を授与されるようなカリスマでしたが、これを引きついだ著者は石原氏のようなカリスマ性ではなく「マネジメントと人材育成」の知識と仕組みにより介護施設運営を工夫していくのがポイントです。
急成長する法人を運営する中で、職員の離職と採用を大量に繰り返していたことや、今後の超少子高齢化の時代において持続的な運営に危機を感じ、コーチングとアメーバ経営を取り入れました。
当たり前だった日本式の介護経営を見直す
かつての日本では人口が増え続ける(マーケットは拡大し、労働者も確保できる)ということが前提でビジネスが成り立っていましたが、介護においても同様の考え方がありました。
分かりやすい例では、コンビニのように24時間空いているようなサービス自体が価値となりビジネスとなるという考え方です。
また、ワークライフバランスという考え方も浸透し、国は働き方改革を推し進めているため旧来の働き方である「長時間労働をすることが素晴らしい」という考え方は180度変わっています。
そのためできるだけ少ない人数で価値の高い仕事を行うかが現在では重要となってきています。
生産性が低いゼネラリスト
日本の社会ではスペシャリストに重きを置かず、何でもするゼネラリストを求めて来た労働慣行や企業風土があります。
一般的にゼネラリストのようなマルチタスク型の人は、スペシャリストよりも生産性が低いとされています。介護業務はまさにマルチタスクで、入浴介助や食事介助のような知識やスキルを必要とする業務から、下膳や掃除などスキルが無くてもできる仕事が多く混在しています。
業務の切り分けをすることで、介護技術のある職員はスペシャリストとしての業務に専念できるような環境を整備する必要があります。
「みんなが同じ」という幻想
欧米では個人主義が根付いており個々人がそれそれ違うことを認め合う文化があります。
よって、例えば障がいを持つ人でもできる仕事を生み出すような仕組みがあります。
しかし、日本の場合は「みんなが同じ」」という幻想があり、自分ができることを、できない人に対して「なぜ、できないの?」と、できない人は使えないと排除するような心理があります。
様々な業務が混合する介護の現場では、働く職員がお互いのできることとできないことを認めて尊重しお互いにカバーし合っていくためのチームワークが必要です。
【当ブログ著者より一言】
日本の教育は製造物の大量生産時代の影響を大きく受けているとされます。読み書きと計算、受験偏重による均質な教育などです。
そのため、日本人は平均的に何でもできることが仕事ができるという定義となってしましまっているのではないでしょうか。
顧客満足度と従業員満足度は切っても切れない関係
本書ではリッツカールトンやネッツトヨタ南国株式会社を例に挙げ、自立的にホスピタリティを提供する従業員や組織風土について記しています。
やり続けられる組織風土を作る
多くの法人、企業では理念を掲げており、どれも素晴らしいことが書かれていますがそれは装飾でしかありません。
重要なのはその組織が何のために存在しているかを示す物語と経営者の情熱です。
著者法人では合掌苑の歴史を収めた動画を作成し、理念共有を図っていきました。そして、毎年、企業計画と目標を定めたハンドブックを作成し全職員に配布しています。
そしてこれらを続けることが重要です。
動画が「創業ものがたり」としてWEBサイトにあります。
コーチングで職員のやりたいことを引き出す
介護職員は多くの場合「人のお世話をしたい」「人を幸せにしたい」というぼんやりとした”目的”をもっているのですが、なかなかそれを明確にできないものです。
そこで役立つのがコーチングです。コーチングとは相手が自ら答えを導き出すことを目的とした対話型のコミュニケーション手法です。
まずコミュニケーションの場を積極的に作るようにしています。他にも、サンクスカード(お互いに感謝の思いを伝え合う)やインカムなどのツールも使っており、このような仕組みも含めて「コミュニケーションの場」としています。
そして、実際に面談の場として著者は1か月で70回(55人)と面談をしています。聞く内容はたいていいつも同じで次のようなことです。
- 前回の面談で「やる」と決めた事はどこまでできたか?
- その中で課題にしていることは何か?
- 次の面談までに何をする?
間違えてはいけないのが、これら目標の達成のために圧をかけるのではなく、あくまでも目標は個人が作成し、何がその目標達成の障壁になっているのかを気づかせてあげることが重要です。
コーチングについては下記書評ページでも記しています。
【書評】『コーチングで病院が変わった 目に見えない道具で「医師の働き方改革」は進化する』 佐藤文彦
従業員自らがやりたいことを目標にするアメーバ経営
組織の目的や目標に従業員のやりたいことをすり合わせることで、従業員は自ら進んで改善意識を持つようになります。
目標は経営数値に繋がったもの(時間当たり採算)にすることで経営者意識を持つようにもなります。
自らの改善活動により数値目標を達成していくことでモチベーションを高め仕事にやりがいを見つけます。
これらの好循環が良い職員満足度の向上、そして良い組織、良い経営(顧客満足度向上)へと繋がっていきます。
まとめと感想
本書で重要なことは、法人と職員のやりたいことを見える化しすり合わせるということと感じました。
そのためのツールとしてコーチングとアメーバ経営を利用しています。
人と言うのはエフィカシー(自己効力感)を得ることが重要と本書には書かれていますが、著者の職場ではエフィカシーを得られるような仕組みを作り出せるようにしているのはとても参考になります。
例えば、サンクスカードはエフィカシーを得るための「言語説得」、アメーバ経営による数値の明確化は「代理体験」「成功体験」という、科学的にも説明がつく要素のようです。
当ブログ著者は医療法人をクライアントとすることが多いのですが医療法人として介護施設を運営している法人も多くあり、このような介護施設に対してもコンサルティングを行っています。
とくに近年は介護施設の生産性向上が国からの至上命令のようになっており、介護報酬上の加算や処遇改善加算のための要件にもなっています。
医療は多くのことが分業されているため、理事長(医師)にとっては気づきにくいのですが介護の現場は分業が進んでいません。介護職を専門職ととらえ、業務整理をし、介護助手やICTにより業務の仕方を変えていくことがまさに生産性向上のために必要なことす。
また、当ブログ著者は三重県からの委託を受け「みえ介護生産性向上支援センター」のコンサルタントとしても活動をしています。

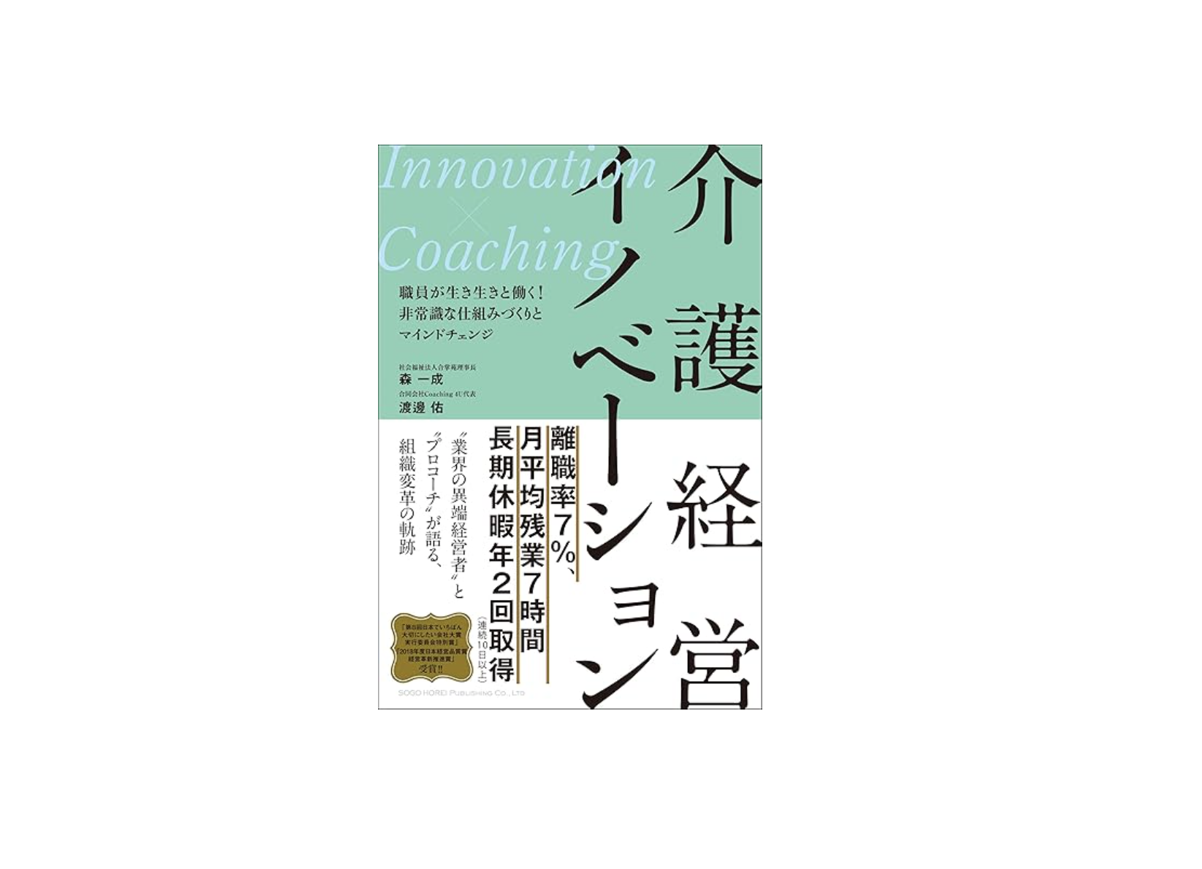





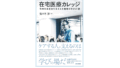
コメント